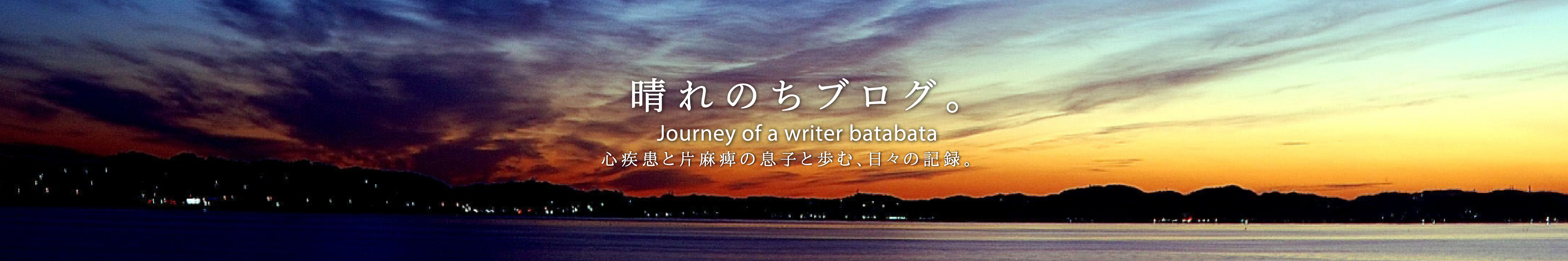こんにちは!tomoです。
先月生まれた子どもが、NICU→小児病棟→退院→妻の実家(里帰り)という流れを辿り、もうすぐ我が家へやってきます。(僕は今はしばしの一人暮らし!)
子どもが生まれると、その後の通院や移動でどうしても考えなくてはならないのが、移動手段ですよね。
移動手段について、ざっと挙げると以下のような種類があります。
- 公共機関(バス・電車)
- タクシー
- 自家用車
- レンタカー(カーシェア)
- 徒歩
我が家のような心臓病を持つ子どもの場合は、専門の病院まで行かなくてはならないので、徒歩は無理だし、毎回タクシーというのも金額がヤバイことになります(病院までそこそこ距離があるので片道7,000円くらい)。
なので、我が家では車を買うか?このまま持たないか?で揺れていました。
結論としては、いずれ持つだろうし、車買おうか。ということに。
そして、気づいちゃいました・・・
カーシェア便利やん!ということに。
もし、頻繁に車に乗らなかったり、よっぽどお金に困っていたのであれば、このまま車を買わずにレンタカー(カーシェア)生活を選択していたと思います。
今回の記事では、レンタカー(カーシェア)に新生児を乗せる場合の注意点・体験談について、書いていこうと思います。
Contents
カーシェアとは
 カーシェア(=カーシェアリング)とは、会員登録をして、特定の自動車を共同使用するサービスのことです。
カーシェア(=カーシェアリング)とは、会員登録をして、特定の自動車を共同使用するサービスのことです。
よくあるレンタカーは、車を有料で借りるサービスに対して、カーシェアリングは特定の自動車を会員間で共有して、それぞれが利用したい時間に借りることができるサービスです。
事前の会員登録が必要で、ステーション(街の駐車場)の車を短時間から借りることができます。
赤ちゃんをレンタカー(カーシェア)に載せる場合の注意点
僕は普段車にあまり乗らないので、知らなかったんですが(もしかして教習所で習ったかも?!)今(2020年現在)の日本の法律上、6歳未満の子どもを自家用車に乗せる場合、安全性の観点からチャイルドシートを使用することが義務付けられています!
違反した場合は、交通違反の基礎点数が1点付加されるので、注意が必要です。
チャイルドシートの義務化はいつから?
着用義務化は2000年(平成12年)4月1日からのようです。(知らなかった…)
その時に6歳未満の幼児にチャイルドシートの着用が義務付けられ、現在に至ります。
以前(十数年前)は、飲酒運転とかシートベルト未着用なんかもある程度は寛容でしたが、交通事故を減らすために、段々厳しくなっていますもんね。
対応年齢・体格をきちんと確認する!
当然ですが、子どもを乗せる場合は体格に合うシートに乗せましょう。
チャイルドシートは、大きく分けて乳児用、幼児用、児童用の3種類のシートがあります。
子どもがそこそこ大きくなると安心してチャイルドシートを使わなくなる…ということを聞いたことがありますが、油断は禁物なので、注意しましょう。
法律上の着用義務は6歳になるまでですが、身長が140センチ未満の間はなるべくチャイルドシートを着用させたほうが良いようです。なぜならば、身長が140センチを超えない子どもはシートベルトを正しく着用できないからです。
ベビーシート(新生児・乳児用)
生後すぐから使用できるタイプがベビーシート。
ベビーシートは、一般的に車の進行方向に対して後ろ向きに設置させるものが多いですね。赤ちゃんを寝かせた状態で車に乗せることができるのが、ベビーシートの大きな特徴です。
カーシェアでレンタルできるところはまだ少ないですが、レンタカーの場合事前に言えばレンタルできるところもあるようです。
ちなみに、僕らは話し合った結果、Joie ベビーシート ジェム エンバーというベビーシートを購入することにしました。
それがこちらです!
新生児~1歳半ごろまで使えるタイプなのですが、 チャイルドシートとしての機能だけでなく、 ベビーチェアやロッキングチェア、さらには指定のベビーカーに取り付けてベビーカー用のシートとしても使用することができる万能なベビーシート。

使える期間は短いですが、ロッキングチェアとして家の中でも使えるので、マイカーを持っていないご家庭にとっては、家の中に置いておけるっていうのもポイントです!
賃貸だから、家は狭いのでね・・・。車を購入した後は、車に常備しようと思います。
チャイルドシート(幼児用)
1~4歳ほどの年齢を対象にしている製品が多く、前向きで使用するタイプと前向きでも後ろ向きでも使用できるタイプがあります。
新生児から使える、ベビーシート+チャイルドシートも長い目で見るとお得です。
その場合は汚れても安心なように、カバーが洗えるタイプが良いと思います。
ジュニアシート(児童用)
ジュニアシートは、4~10歳ほどの年齢を対象にしたチャイルドシートです。
対象年齢が幅広いため、年齢に合わせてヘッドレストや背もたれを取り外せるものや、最初からヘッドレストや背もたれのないものなど、様々なタイプがあります。
基本的には、ジュニアシートに座らせることで子どもの座高を上げて、大人と同じようにシートベルトが使える状態にするシートです。
カーシェアの場合、車に付属されていて自由に使える場合もあります。
チャイルドシート(ベビーシート)の取付け方法は念入りにチェックしておく!

退院時にチャイルドシートを使う場合は、ほとんどの方が初めて使うっていう方が多いんじゃないでしょうか?
いざ、退院!と思ってレンタカーを借りたは良いものの・・・チャイルドシートの取り付けにまごついてしまうという方も少なくありません。
今の時代、取り付け方はネット上にたいていありますし、できたらYouTube等の動画を事前に見ておくことをおすすめします。僕も子どもの退院日の前日には動画を見ながら何度もイメージトレーニングをしました(^^;
しっかりと取り付けができていないと、安全性を100%引き出すことができないですからね。
もちろん、安全運転で!
赤ちゃんや子どもを乗せる場合に限らず、そして、レンタカーやカーシェア、マイカーに限らず、安全運転を常に心掛けましょう!
今は、安全装置がついている自動車も増えてきましたので、できたら安全装備が万全な車を選ぶと良いですね。
出産退院後に、赤ちゃんを抱っこして車に乗っていいのか?
自家用車でもレンタカーでもカーシェアでも、子どもを乗せる場合はチャイルドシートは必需品です。
「えっ、抱っこで良いんじゃないの?」
・・・って、僕も知人から言われたことがあるのですが、
チャイルドシート未使用だと交通違反になるので注意です!
それは、出産後の退院時も当然同じ。
特に、親世代の方だと時代が違うので、交通違反になるという認識がないのかもしれません(^^;
新生児など、寝たままの姿勢の月齢の赤ちゃんでも、成長具合に対応したチャイルドシートを使用しなければなりません。大人が抱いて乗せることはもちろんNGです。
出産後にタクシーに乗車して退院する場合は?
マイカーを持っていないご家庭では、レンタカーやカーシェア以外だと、タクシーを利用して退院する方法が考えられます。
調べたところ、道路交通法によれば、タクシーの場合はチャイルドシートを使わなくても法律的には問題ありません。
例外的に「チャイルドシート使用義務免除」される場合は以下の通り。
・バス
・タクシー
・幼稚園バス(※座席が幼児用のため)
・負傷している等療養上適当でないとき
・著しい肥満など体型に合わないとき
・授乳やおむつ替えのとき(※必ず停車しましょう)
・応急救護の搬送
・迷子の子供を警察署へ送り届けるとき
など
基本的には、一般旅客運送事業や、緊急時などやむを得ない場合は使用義務が免除される場面があります。「やむを得ない場合」というのが、ちょっとグレーな感じではありますが・・・。
以外なのが、タクシーでは法律上は免除されているという点。
じゃあ「赤ちゃんを抱っこしていいよね!」と思う方もいますが、何か起きてからでは遅いので大変危険です。運転手さんがいくら熟練のプロドライバーでも、人間が運転する以上、絶対安全とは言い切れません。
タクシー会社では、子育て世代向けに提供しているサービスも最近増えてきました。
キッズタクシー | 日本交通のエキスパートドライバーサービス
予約する際に「チャイルドシートはありますか?」と聞けば、無料~数百円程度で用意してくれる場合も。
もしチャイルドシートを持っていない人は、一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
新生児の退院時に限らず、病院への通院などにおいて移動手段は考えなくてはなりません。
自家用車でもレンタカーでもタクシーでも、バスでも、どれも正解だと思いますが、
一番大切なことが、命を守ること。
そのためには「計画を立てる」ということが第一歩であると、僕は考えます。
- 病院から家までのルート・所要時間を確認
- 移動手段を確認(公共機関?タクシー?レンタカー?カーシェア?)
- どのチャイルドシートを買うか?
- チャイルドシートの付け方を確認